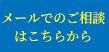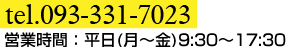遺言書の作成
しかし、公正証書遺言の作成件数は年々増加しており、平成26年にはついに10万件を突破。
これは公正証書遺言には「相続手続に必要なお金を節約できる」「遺産相続手続がとても楽になる」というメリットの方が大きく、ケンカするほど遺産がない方、相続人に面倒をかけたくない方にこそメリットの多い書類だということが広まってきた結果だと思います。
目次(知りたい項目をクリックするとジャンプします)
- 一 遺言書を書いた方がいい人
- 二 遺言書の内容の決め方
-
- 01 遺産になる財産の整理
- 02 遺産ごとに引き継ぎ先、寄付先を考える
- 03 条件を付けるかどうかを検討する
- 04 遺留分に配慮する
- 05 死亡保険を活かす
- 06 遺言執行者を決める
- 07 財産に関すること以外に書けること
- 08 相続税の問題を考える
- 09 遺産を全部又は割合で指定する場合
- 三 遺言書と一緒に考えたい相続の準備
-
- 01 エンディングノートとは?
- 02 尊厳死宣言証書(リビング・ウィル)とは?
- 03 生前贈与の活用
- 04 遺贈寄付の活用
- 05 成年後見制度の活用
- 06 任意後見制度の活用
- 07 遺言信託の活用
- 四 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
-
- 01 比較表
- 02 検認で起きる問題
- 03 自筆証書でも十分な場合、公正証書遺言が必要な場合
- 五 自分で作る遺言書の書き方
-
- 01 自筆証書遺言の必須条件
- 02 不動産の書き方
- 03 預貯金の書き方
- 04 投資信託の書き方
- 05 株式の書き方
- 06 「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
- 07 遺言執行者の書き方
- 08 条件付き条項の書き方
- 09 配偶者居住権の書き方
- 六 ご契約と手続きの流れ(自筆証書遺言の場合)
-
- 01 ご相談、お見積りと契約
- 02 原案の作成
- 03 費用の御支払い、原案のお渡し
- 04 用紙への記入・立会人の署名捺印
- 05 確認、封印
- 七 ご契約と手続きの流れ(公正証書遺言の場合)
-
- 01 ご相談、仮契約
- 02 原案の決定
- 03 公証役場の費用見積を依頼、正式契約
- 04 公証役場での面談若しくは出張+証人2名の立会い
- 05 費用の支払い、遺言書正本の受領
- 八 主な費用
- 九 当事務所にご依頼いただくメリット
一 遺言書を書いた方がいい人
福岡県内で家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いは福岡県内だけでも年間で約500件。
もはや他人事ではなくなった遺産相続を巡る問題を避けるため、基本的にはどんな方にも遺言書を作っていただきたいのですが、経験上、特に以下の8つに該当する方は大きな問題に発展する可能性が高い傾向にあります。
01 不動産(自宅を含む)を所有しているが、預貯金は多くない
不動産は現金や預金のように物理的に分けて分配することが非常に困難です。
土地であれば分筆することもできますが、二つ以上に分けると価値が極端に下がる若しくは利用できなくなることも多いです。不動産を共有させることもできますが、売却や大幅なリフォーム、担保にする等何をするにも共有者全員の同意が必要になりますし、固定資産税を誰が負担するかも難しい問題です。収益物件なら賃料の取り分、賃貸の管理、クレームの対処、修理の責任等々、不動産を共有すると何かと問題が発生しやすくなります。
そこで、不動産は一人に継がせる方が良いのですが、比較的価値の高い財産なので遺産配分に偏りが生じてしまいます。
現金や預貯金でその差を調整することができるのであれば良いのですが、調整できる遺産がない場合、相続人に不公平感が残ってしまいます。
遺言書が無い場合は遺産分割協議をしなければならず、結果として誰かの取り分が少なくならざるを得ませんから、これが原因で感情的な対立につながることがよくあります。取り分が少ない相続人に相応のお金(俗に言う「ハンコ代」「印鑑代」)を渡せば諦めてもらえるかもしれませんが、そのお金を準備することが出来なければ不動産を売却して現金を分けるくらいしか方法がありません。と言っても売ることのできない不動産であればどうしようもありません。
不動産を継いでほしい人が安心して受け取れるように遺言書を作成しておき、遺産の取り分が少なくなってしまう相続人には別の対処法を考えるべきです。
02 自分名義の土地に親族が家を建てて住んでいる
例えば、親名義の土地の上に子供(又は子供の配偶者)が自宅を建てているケースです。遺言書が無い場合、その親が亡くなると土地を誰が相続するのか?という問題が発生します。その土地の上に住んでいる子供としては当然に自分が相続したいと思うでしょうが、他の相続人としては面白くありません。その子供が親名義の土地を無償で使用してきたことに対して他の相続人が不満を感じていた場合、遺産分割協議で上手く纏まらないことはよくあります。もちろん、その土地を使用してきた子供にも言い分はあるでしょうが、その言い分に他の相続人が納得するかどうかは分かりません。
この事例のようにご自身の財産が家族や近しい方の衣食住を支えている場合、相続手続きに関連して生じる問題がその方の日常生活を不安定にさせる恐れがあります。こうした問題を避けるためには遺言書で確実に対処したうえで、早めに対策を立てておくべきです。
03 自分の相続人になる予定の人で高齢者又は音信不通の人がいる
まず、遺産分割協議は相続人全員が合意の意思を示すことが絶対条件です。従って相続人の中に一人でも意思表示ができない相続人がいると遺産分割協議は成立しません。もちろん、意思表示のできない相続人の代理人を家庭裁判所に選んでもらう手続きはありますが、時間もお金もかかりますし、遺産分割協議も家庭裁判所が許可を出さないと成立しませんので、遺産分割の内容も当初の予定とは大きく変わってしまうおそれがあります。
よく「遺産の分け方については前に話し合っていた」とか「今は話ができないけど、まだ元気だったときに承諾はもらっている」と言われますが、以前はどうであれ遺産分割協議書に署名、捺印する段階でしっかりと意思表示ができない限り遺産分割協議書としては認められません。
対して、万全な遺言書を作成しておけば遺産分割協議自体が不要になるのでこうした問題は発生しません。遺言書によって財産を受け取る人がしっかりと意思表示ができる状態であれば、他の相続人がどのような状態であろうと関係はありません。
04 子供がいない
出生から死亡するまで子供がいなかった場合、相続人は配偶者と被相続人の直系尊属(親、祖母、祖父母)となりますが、被相続人が高齢であればその直系尊属は既に死亡して誰もいない場合が殆どです。そうなると被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となりますが、相続人が子供の場合と比べて配偶者と兄弟姉妹間、あるいは兄弟姉妹間でトラブルになりやすい傾向にあります。
特に被相続人が高齢で亡くなった場合はその兄弟姉妹も既に高齢であることが多く、遺産相続の話自体が理解できないことも少なくありません。
このような場合は事前に遺言書を作成しておくことで配偶者、兄弟姉妹間での対立を予防するだけでなく遺産分割の話し合いをしなくても済むように配慮しておくことができます。
05 離婚歴がある
自身に離婚歴がある場合は誰が相続人になるかに注意が必要になります。前婚者との間に自身の子供が産まれていた場合、その子供は相続人となります。これは離婚した後であっても変わりません。前婚者の子供と再婚後の家族との間でコミュニケーションができているなら良いですが、断絶状態であれば印鑑をもらうのも大変です。更にその子供が亡くなっているとその親族に相続権が移るので他人同然の人と遺産相続の話し合いをしなければならなくなります。
こうした事態も遺言書を作成することで予防できます。
なお、そもそも再婚の事実、遺言書の存在自体を出来るだけ秘密にしたい場合は公正証書による遺言書でなければなりません。自筆の遺言書の場合は手続上、必ず相続人全員に裁判所(自筆の遺言書を法務局に保管していた場合は法務局)から通知が届くことになります。これにより親族全員に離婚と再婚の事実も遺言書の存在も全て知られてしまいます。
06 お世話になった人(団体)に寄付・遺贈したい
遺言書が無い場合、遺産を受け取る権利があるのは相続人のみです。例えばお世話になった団体や施設、NPO、慈善団体等に寄付したい場合は遺言書が必須になります。あるいは、内縁者や配偶者の連れ子等は養子縁組をしない限り相続人には当たらないので、それらの方に遺したい場合も同様です。
なお、外部への寄付や遺贈を検討する場合は通常の遺言書作成よりも注意しなければならない点が増えるため難しくなります。必ず専門家にご相談をお願いします。
07 自身が経営している会社又は親族等が経営している会社に出資して株式を持っている
どんなに小さな株式会社でも一部の例外を除き、出資すれば株主になります。そして、原則として株主はその会社の経営に口出しできる権限を有します。そのため、経営方針に批判的な株主や無関心な株主がいると会社は大きなリスクを抱えることになってしまいます。
遺言書が無い場合、保有している株式も遺産の一部となり遺産分割協議によって相続人で分けます。社内にいる相続人に渡るのであればまだ良いのですが、事業に関与していない、あるいは現在の事業に否定的な相続人が相続することもあります。そして、誰に新しい株主になってほしいかについて会社が口出しする権限はありません。
例えば、会社の取締役を変更するにも再任するにも株主となった相続人の承諾が必要になります。その相続人が大部分の株式を相続した場合は会社の解散権すら握られてしまいます。赤字でも黒字でも関係なく、突然に望まぬ株主が会社の命運を握ってしまうのです。
自身が所有する株式が自身や親族・友人等が経営する会社の株式であれば、その会社に迷惑をかけないよう自身の株式を誰に引き継がせるべきか会社の関係者とも話し合ったうえで遺言書で指定するべきです。
08 自身が死んだ後の手続きは安く早く済む方がいい。
相続に関係する手続きは、どのような方法であろうと数万円~十数万円の費用がどこかで必ず必要になります。公正証書遺言を作成する場合は公証役場に作成手数料を払わなければなりませんし、自筆の遺言書であれば遺産相続手続前に「検認」(家庭裁判所で行われる遺言書の開封手続)が必要なのでそこで費用が発生します。遺言書を作らないのであれば相続人が遺産相続手続にかかる費用を負担しなければなりません。
自筆の遺言書を作成し、法務局で保管する制度を利用した場合は検認が不要になるため、コストは抑えられますが、相続人が写しの交付申請を行う際には申請書、戸籍謄本等の書類が必要になりますので、それなりの手間とコストがかかります。
では、コストの部分だけを言えば、遺言書は書いても書かなくても同じでしょうか?
それは違います。まず費用の負担者という面から考えると、公正証書遺言の場合は財産を保有している当人が負担しますが、自筆の遺言書と遺言書の作成無しの場合は相続人が負担します。遺言者自身がその金銭負担を負う方がいいと考えるのであれば、公正証書遺言を作成するという選択になります。
遺産相続手続に支障が生じるリスクや負担感という面から考えると、公正証書による遺言書作成が最も低く、遺言書がない場合が最も高くなります。財産があってもなくても遺族は葬儀や法要等で大きな負担を背負います。これはどうしようもないことではありますが、少なくとも遺産相続手続に関わる負担だけは生前に済ませることが可能なのです。
「相続人や親族に負担をかけなくない」
「遺産相続で発生する手間やリスクをできるだけ抑えたい」
この二点を重視するのであれば、公正証書による遺言書作成をお勧めします。
- Q:遺言書はいつまで作成できますか?
- A:手書きの遺言書であれば、字が書けるまでです。代筆は認められません。また、自筆の遺言書を法務局で保管してもらうのであれば、法務局に行き、窓口で遺言書保管制度の利用を申請できる状態でなければなりません。
公正証書遺言であれば、字が書けなくても意思疎通が可能であれば作成できます。いずれにしろ、意思疎通が完全に可能である間に作成しなければなりません。
- Q:遺言書を書いたのですが、気が変わったので財産を手放してしまおうと思います。
- A:遺言書に書いたからといってその財産を所有し続ける義務を負うわけではありません。遺言書に記載された財産が既に無い場合でも遺言書自体が無効になるわけではなく、その遺産に関する記載だけが実現不能になるだけで他の記載には影響ありません。
ページのトップへ
二 遺言書の内容の決め方
遺言書を書こうと思っているが何から始めたらいいか分からない、という方もおられると思います。
そんな方は、まずは「誰に何を継がせたいか?」を考えることから始めてみましょう。
01 遺産になる財産の整理
まずは遺産となりそうな自身の財産を整理してみましょう。
特に遺言書に記載して引き継ぎ先を指定した方が良い財産としては、
- ■ 不動産
- ■ 預貯金
- ■ 株式
- ■ 投資信託
- ■ 宝石等の貴金属、絵画、骨とう品など
- ■ 負債(住宅ローン、損害賠償、借金、誰かの保証人になっていること、事業融資、養育費等)
が一般的ですが、その他に相続人に伝えておきたい財産があればそれも付け加えます。この段階ではとにかくリストアップだけで大丈夫です。
注意点としては「負債も遺産になる」という点です。住宅ローンは団体信用生命保険に自身が加入しており保険の適用が受けられるのであれば問題はありませんが、その他の負債については相続人が負担を引き継がなければならなくなる可能性があるため、きちんと記載しておくべきです。
ただし、負債については遺言書で承継者を指定したとしても債権者が同意しない限り他の相続人も責任を負います。
02 遺産ごとに引き継ぎ先、寄付先を考える
引き継ぎ先を考える順序としては、先に物理的に二つ以上に分割して引き継がせることが難しい財産から決めた方がスムーズです。
コツとしては、相続人間の公平性を維持することにこだわりすぎないことです。金銭的な部分よりも「誰がその財産を引き継ぎ、管理すべきか?」を優先して検討すると良いと思います。
- (1) 引き継がせたい人(団体)以外が引き継いでしまうと問題が生じる重要な不動産・株式
- そもそも受取人に変更の余地がない遺産です。例えば、子供が住んでいる家の敷地が遺言者所有の土地である場合などです。あるいは自身が経営する会社又は身近な人が経営する会社の株式も今後の事業を考えながら誰に遺すべきか最初に決定します。
- (2) (1)以外で指定の人(団体)に遺したい不動産・株式
- (1)は引き継ぎ先を変更しにくい財産ですが、(2)は「絶対ではないが、継いでほしい人が決まっている財産」です。
不動産については収益物件か非収益物件かで価値が変わってきます。収益物件は賃料収入が発生しますが維持管理は大変です。その不動産を借りている人の生活にも影響しますので適切に維持管理できる人に継がせるようにしましょう。対して非収益物件あるいは既に収益性が低くなってしまった不動産は実質上負債に近く誰に引き継がせるか悩むかと思います。
不動産は比較的高額な財産ではありますが、家族関係、資産状態、維持管理費、収益性等難しい部分が多く決めにくいかと思います。自分一人で決めるのではなく相続人や関係者とも話し合って決める方が無難です。
- (3) 投資信託
- 投資信託は不動産と異なり維持管理がそれほど難しくなく換金性も高いので預貯金に準じて考えます。ただし、資産価値が流動的なので、遺言者が亡くなった時点で値下がりしているリスクはあります。
- (4) 現金・預貯金
- 相続人間の公平性を考慮するのであれば、預貯金で調整することが多いです。あるいは特定の相続人の生活費として遺すこともあります。
注意点として遺言書には「○○に△△万円を相続させる」というように金額で指定するのではなく、「○○に2分の1を相続させる」というように割合で指定する方が安全です。現金や預貯金は変動が大きいため金額を固定してしまうと不都合が生じるおそれがあるためです。
03 条件を付けるかどうかを検討する
遺言には条項ごとに「その財産を受け取るための条件」を付けることができます。例えば、「飼い犬の世話をすることを条件に、その世話代として…を相続させる」等です。
また、もし財産を受け取る予定の人が何らかの事情により受け取ることができなかった場合に代わりに誰が受け取るか指定することができます。財産の引き継ぎに関する遺言は「遺言者が死亡した時点でその財産の受取人が存命していること」が必要です。もし、遺言者が死亡した時点でその財産の受取人が死亡していた場合はその条項が実現不可能となり、通常の遺産として遺産分割協議が必要になってしまいます。こうした事態を避けるため、
「相続人Aに○○を相続させる。もし、遺言者よりも先にAが死亡していた場合はBに相続させる」
などのように条件を定めておくことで遺産分割協議が必要になってしまうリスクを予防します。
04 遺留分に配慮する
遺留分とは「一定の相続人に保証された相続分」です。遺留分を無視して遺言書を作成することもできますし、遺留分を主張するかどうかはその相続人の自由です。しかし、遺留分を侵害してしまうような遺言書を作成する場合は相続人に対して理由をしっかりと伝え、納得してもらうことが大切です。
遺留分の請求を受けた場合、その遺留分の請求が適法であるならば、その遺留分に相当する金銭を、請求してきた相続人に払わなければなりません。遺留分の請求権は強力な権利なので、請求額を含めて適法であれば拒否することはできませんし、訴訟となれば、支払いの猶予期間を設定してもらえることはありうるものの、よほどの事情がない限り支払い自体を免除されることはありません。それでも支払いを拒否し続けると財産を差し押さえられてしまうこともあります。
請求に備えて相当額の金銭を生前贈与しておく方もおられますが、その金額自体が遺留分の対象として計算に含まれてしまう可能性もあり、結果的に請求される金額が増えて対策にならないこともあります。こうした問題を避けるため、生命保険等を活用する方法もあります。
- 1. 配偶者と直系卑属が相続人になる場合
-
配偶者の遺留分 遺産×4分の1
直系卑属の遺留分 (遺産全体×4分の1)÷相続人となった直系卑属の人数
※相続人となる直系卑属とは「被相続人が死亡した時点で存命している直系卑属のうち、被相続人に一番近い親等の者」です。
- 2. 直系卑属のみが相続人になる場合
- 直系卑属の遺留分 (遺産×2分の1)÷相続人となった直系卑属の人数
- 3. 配偶者と直系尊属が相続人になる場合
-
配偶者の遺留分 遺産×6分の2
直系尊属の遺留分 (遺産×6分の1)÷相続人となった直系尊属の人数
- 4. 直系尊属のみが相続人になる場合
- 直系尊属の遺留分 遺産×3分の1÷相続人となった直系尊属の人数
- 5. 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
-
配偶者の遺留分 遺産×2分の1
兄弟姉妹の遺留分 無し
※被相続人よりも相続人になる兄弟姉妹が先に死亡していた場合はその子(被相続人から見て甥・姪)が相続人になります。
- 6. 兄弟姉妹のみが相続人なる場合
- 兄弟姉妹の遺留分 無し
- 7. 配偶者のみが相続人になる場合
- 配偶者の遺留分 遺産×2分の1
- 8. 遺留分の対象となる遺産
-
遺留分の対象財産の計算方法は多少特殊です。(1)と(2)は把握しやすいのですが、(3)(4)(5)は証明が困難なので、加算するためには相手方が認めない限りは確かな証拠が必要となります。
(1)被相続人が相続開始時点で保有していた財産
(2)被相続人の死亡日からさかのぼって1年以内にされた相続人以外への生前贈与
(3)被相続人の死亡からさかのぼって10年以内にされた相続人への生前贈与(婚姻若しくは養子縁組のためにした生前贈与又は生計の資本としてした生前贈与に限る)
(4)当事者双方がその贈与により遺留分が侵害されることを知っていた場合はその生前贈与
(5)当事者双方が、遺留分が侵害されることを知っていながら不相当な価格でした売買等
※生計の資本としてした贈与とは、生活の基盤となりうるような財産の無償提供行為を言います。お年玉や多額でない生活費の援助、他の相続人と比べても不相当に高くはない学費の援助などは含まれません。対して、相続人の自宅の敷地を贈与した、あるいは相続人の起業のため相当の資金を提供した場合は生活の基盤となりえますので「生計の資本としてした贈与」と考えられます。実際には、贈与した金額、被相続人の社会的地位、資産状況、贈与の目的等、諸事情を考慮して判断されます。
- 9. 遺留分の請求ができる期限
-
遺留分を請求するかどうかはその相続人の任意ですが、遺留分を有する相続人は(1)又は(2)のいずれか早い日までに請求しなければなりません。
(1)被相続人の死亡及び自身の遺留分が侵害されていることを知った時から1年以内
(2)被相続人の死亡から10年以内
05 死亡保険を活かす
まず原則として相続人等が受け取った死亡保険の保険金は遺産ではありません。これを上手に活用することで遺留分の対策を立てることができます。
例えば、遺留分の請求を受けそうな人(団体)を保険金の受取人にして契約します。遺留分の請求に対しては侵害された遺留分相当の金銭を払えば良いので、自身の死後、もし遺留分の請求を受けた場合はその保険金を支払いに充てるように伝えておけば遺留分の争いを早期に決着することができます。
また、死亡保険金は相続人間の不公平を調整するために使われることもありますし、死亡保険を相続人が受け取った場合に限り、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が適用されますので相続税対策にも使われます。
06 遺言執行者を決める
遺言執行者とは遺言書の内容を確実に実行するために指定される代理人です。事前に遺言書中で指定する場合と被相続人の死亡後に家庭裁判所で選任してもらう場合があります。とはいえ、執行者がいた方が何かと都合が良いので、事情に関わらず遺言書による事前指定をお勧めしています。
なお、執行者は未成年者・破産者以外であれば財産を受け取る人本人であっても構いません。ただし、任せられそうな人がいない場合は外部の弁護士や司法書士等の専門家を執行者に指定することがあります。費用はかかりますが、専門家であれば不測の事態(例えば、遺産の受取人が認知症になっていた、遺産の一部を相続人が勝手に使っていた等々)にもすぐに対応することができます。
特に外部の専門家を遺言執行者に指定した方が良い場合は、以下の三例です。
- 1. 遺産の全部又は一部を相続人以外に渡すとき
- 遺言書によって相続人が遺産を受け取る場合はその相続人だけで手続を行うことができます。しかし、遺産の受取人が相続人以外である場合は相続人と受取人の双方が協力して手続きを行わなければならないこともあり、事情によっては遺言書の内容が実現できなくなるリスクもあります。こうした場合に遺言執行者がいれば相続人の協力は不要になるので、より確実です。
- 2. 遺言書の内容に相続人が従わない可能性があるとき
-
仮に適法な遺言書があったとしても、遺言書で遺産分割協議が禁止されていない限り、相続人全員が合意すれば遺言書通りでない遺産分割も可能とされています。また、遺言書で遺産分割協議が禁止できる期間は遺言者が死亡してから5年間ですので、これ以降は自由に遺産分割ができます。
対して遺言執行者に専門家を指定したうえで、遺言書の謄本をその専門家が所持しておけば相続人が勝手に遺産分割協議をすることを未然に防ぐことができます。
- 3. 遺産の受取人が事情により遺産の受取手続ができないとき
- 例えば遺産の受取人が高齢で銀行の窓口等に行くことができないときは執行者が代わりに手続きを行うことができます。受取人の健康状態などに不安がある場合は専門家による遺言執行をご検討ください。
07 財産に関すること以外に書けること
遺言書には財産に関することの他に様々なことを記載することができます。
- 1. 認知
- 婚姻関係にない男女の間に生まれた子供を父親が「自分の子供である」と認めることです。これによって認知された子供は相続権を持つようになります。実際の認知届は遺言執行者が提出しますので、遺言書で執行者を指定していない場合、別途家庭裁判所で執行者を選んでもらう必要があります。
- 2. 相続人の廃除
-
相続人の廃除とは「遺留分を有する相続人」を「家庭裁判所の許可を得て」「相続人から外す」手続きです。許可が必要なので遺言書に「相続人○○を相続人から廃除する」と書いても無条件に認められるわけではありません。
遺言書を使えば遺言者の好きなように遺産を配分することができますが、遺留分を奪うことはできません。ただし、一定の事由があり、その事由を家庭裁判所が認めれば遺留分を奪うことができます。これが相続人の廃除です。一定の事由とは、被相続人の虐待や重大な侮辱等ですが、実際に廃除が認められることは多くありません。
- 3. 付記事項(メッセージ)
-
付記事項は法律的に意味があるわけではありませんが、感謝の言葉や遺言書を書いた経緯、何故このような遺産の分け方をしたのかの理由、相続人一人一人へのメッセージ等々何でも大丈夫です。
遺言書は非常に無味乾燥な書面です。自筆の遺言書であれば手書きなのでまだ良いのですが、公正証書遺言はパソコンで作成されますので味気ない見た目になってしまいます。そこで、付記事項としてご自身の心の内を記載することで気持ちも遺せる遺言書になります。
経験上、この付記事項が意外と重要で相続人間の無用な対立を防ぐ力もあります。
08 相続税の問題を考える
遺言書の内容を考えるとき、相続税対策を優先することはあまりお勧めできません。相続税対策を意識しすぎて相続人に不満が出てしまうと意味がないからです。あくまで相続で問題が起きないようにすることを重視し、相続税対策は出来る範囲で考えましょう。
相続税対策を考える場合は、そもそも自身が亡くなったら相続税が課税されるのかどうかを確かめなければなりません。実際の計算は税理士に相談いただく必要がありますが、ざっくりと課税されそうな財産を計算してみて相続税の基礎控除「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」に近い金額であればご相談いただいた方が良いと思います。相続税の課税が避けられないようであれば、納税資金を事前に用意しておく等の対処が必要になります。
相続税が課税される遺産とは?
- (1)被相続人が死亡時点で保有している財産額(金銭に換算することのできる経済的価値のあるもの全て)
- (2)死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険の死亡保険金額(但し、控除制度あり)
- (3)相続や遺贈で財産を取得した人が被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の生前贈与を受けたことがある場合は、その財産額(但し、控除制度あり)
- (4)生前に相続時精算課税制度の適用を受けていた場合は、制度適用後に贈与された財産額
- ※控除制度には適用条件があり、必ず適用できるわけではありません。
09 遺産を割合で指定する場合
遺産ごとに引き継ぎ先を決めることもできますが、「遺産の2分の1」のように割合で指定することもできます。但し、具体的に分けようとすると結局は遺産分割協議をせざるを得ません。遺産が金銭のみの場合など「話し合わずとも割合で分けられるもの」のみであれば支障はないですが、そうではない場合は遺産ごとに指定した方が無難です。
ページのトップへ
三 遺言書と一緒に考えたい相続の準備
遺言書の作成と併せて知っておきたいツールや制度について御紹介します。
01 エンディングノートとは?
遺言書は大事な物ですし極めてプライベートなことも書かれるので、あまり外部の人に見せるものではありません。またあまり細々と書くのも大変です。
そこで「遺言書には書けないけど、家族に伝えておきたい事項」を書くものがエンディングノートです。特に決まった形式があるわけではありませんが、特徴として認知症になった場合の介護・治療方針の希望、危篤状態になったときの対応や葬儀の方針等、自分の意思を示すことができなくなった段階から死亡後に至るまで自身の希望を周りの人に伝えることができるようになっています。
特に葬儀の内容については、突然家族を亡くされて動揺している中、業者に言われるがまま任せてしまった結果、葬儀費用が高額になってしまったという事例も少なくありません。
ある葬儀業者の方から聞いた話ですが、「エンディングノートのような亡くなった本人の希望が分かるような書面があれば尊重している」そうです。
本人の希望は口頭で伝えておいても効果を発揮するとは限りません。形に残るもので伝えてこそ効果があるものです。
エンディングノートは市販されていますし、相続や葬儀関係のセミナー等で簡易なものが配布されることもあります。
・介護の希望、資産管理を任せたい人の連絡先(弁護士、司法書士等)
・かかりつけ医のいる病院名、連絡先
・危篤時の治療方針、臓器提供の意思の有無
・連絡してほしい親族・友人リスト
・宗派、寺社、葬儀業者の希望
・葬儀・法要の希望(家族葬を希望する、戒名の要否、三回忌までで良い等々)
・携帯電話の番号(解約がスムーズに出来るようにするため)
・印鑑、通帳、保険証券等の貴重品の保管場所
・定期的に支払っているものがあればその解約連絡先
・ネットバンキング等のインターネットを通じたサービスを利用している場合はその解約連絡先
・資産のリスト、負債のリスト
・加入している保険の内容
02 尊厳死宣言証書(リビング・ウィル)とは?
自分の意思を示すことができないまま死期が近くなった際に、医師や周りの家族にどのように対応してほしいかを記載した書面です。特に延命治療、胃ろう、痛みの緩和措置等の希望を短くまとめます。安楽死や脳死の問題がクローズアップされて以降、作成する方が増えていますが、実際の現場では延命治療を打ち切るかどうかを判断するのは医師なので、尊厳死宣言証書は殆どの医療機関で尊重されるものの、医師に法的義務が生じるわけではありません。
エンディングノートに書くこともできますが、尊厳死宣言証書は本人の署名・捺印がされますので、本人の真意に基づくものであることがより確かになります。さらに尊厳死宣言証書を公正証書で作成すると万全です。
03 生前贈与の活用
遺言書で全財産を引き継がせても良いのですが、生前に贈与しておくことで後々の面倒を減らすことができます。ただし、生前贈与は贈与税、登録免許税(不動産の名義変更時に課税される税金)、不動産取得税等、相続時よりも高額な税金が課税されやすいという欠点があります。生前贈与を検討中の場合は贈与税を回避するための特例を適用できるかどうかも含めて検討する必要があります。
また、生前贈与は税金の問題とは別に相続人間で感情的な対立が起こる原因にもなる手法です。口約束で贈与するのではなく贈与契約書を作成し、専門家立会いで署名・捺印する方が安全です。
04 遺贈寄付の活用
遺言書を使えば、遺産をNPO法人等の公益団体に寄付することもできます。また、預金からの寄付であれば寄付額がそのまま相続税の課税額から控除されますのでリスクの低い相続税対策にもなります。ただし、今のところ現金・預貯金等以外の寄付を受け入れている団体は少なく、換金性の低い財産の寄付は難しいのが実情です。
有名な大きな団体はホームページ等で遺贈寄付の受け入れを表明していますが、小さな団体は遺贈寄付の受け入れが可能かどうか事前に相談する必要があります。お世話になった団体やボランティアで関わったことのある団体があればそちらに相談してみるのも良いと思います。
遺贈寄付は自身の遺産を社会貢献のために有効に利用してもらうことができますが、法的に慎重な検討を要する要素も多く、想定外のトラブルも起こります。
遺贈寄付を行う際は法律専門家のアドバイスを受けることも大事ですが、相続人の遺留分に注意することと遺言執行者として外部の法律専門家を指定することが重要になります。また、遺言書は公正証書遺言で作成するようにしてください。
当事務所では、お客様の希望も伺いながら、寄付団体の提案から団体への説明、遺言執行もしっかりサポートさせていただきます。
05 成年後見制度の活用
遺言書を作成した後、仮に認知症等で自身の財産管理が困難になったとします。認知症の中には不要な物を次々と購入してしまうという発症の仕方もありますし、高齢者を狙った悪徳商法被害も少なくありません。そうなるとせっかく遺言書で遺産を遺そうとしたのに気が付いた時にはその遺産が無くなっていたということにもなりかねません。
そういったリスクを防止するため、家庭裁判所にその方の代理人となる人を選んでもらい、財産を管理してもらうことができます。後見人は印鑑や通帳を預かり、施設の料金支払いや年金の受け取り等を代行し収支を1円単位で帳簿に付けて管理します。後見人は定期的に収支報告書を作成して家庭裁判所に提出し不審な点はないか確認を受けなければなりません。
後見人は親族でもなることができますが、日々の帳簿付け、家庭裁判所への定期報告等が煩雑なことに加えて、責任も重くよほどの事情が無い限り途中で辞めることもできません。
そこで、後見人の業務を専門とする司法書士や弁護士等の法律専門家に後見人になってもらうことで親族に負担をかけることなく、公平公正な第三者に財産管理を任せることができます。
06 任意後見制度の活用
任意後見制度は簡単に言うと「まだ元気だけど、もし私の意思能力が危なくなったら、あなたがすぐに後見人になってね」と依頼して契約しておくことです。いわば、「成年後見の予約制度」です。
通常、成年後見人を選んでもらうためには、配偶者か四親等内の親族から家庭裁判所に申立書を提出する必要があります。普段から親族と交流があり自分の健康状態が分かっている人が身近にいるなら、その人が認知症に伴う言動や行動の変化に気づくことができるので、その人が申立人になって成年後見人の申立手続きを行うことができます。しかし、身寄りがない、あるいは親族が遠方で一人暮らしをしている方は健康状態が悪化してもすぐに気付ける人がいません。結果、警察や行政が関与して初めて親族が健康状態の悪化を知るということもあります。
こうした事態にならないよう、元気なうちに任意後見人を頼んでおき、定期的な訪問を依頼しておきます。任意後見人は本人が元気な間は契約で定められた事項のみを行い、本人の意思能力が低下した場合にすぐに自らが申立人になって家庭裁判所に後見人選任の手続きを行います。
普段から交流のある親族がおらず、自宅に一人暮らしをしている等の場合はご検討ください。
07 遺言信託の活用
法律的な意味とは違いますが、遺言書の作成と併せて当方を遺言執行者とすることで不動産・預貯金・投資信託・株式等の相続手続きも含めて当方に「全部お任せ」されるご依頼形態です。金融機関・証券会社の窓口には全て当方が出向き、申請書類の準備や打ち合わせを行います。
遺言者の死亡後、当方が遺言執行者として相続人等への通知、財産目録の作成から関係者の調整、窓口での手続を行います。
一部の例外を除き、全て遺言執行者が手続きを代理できるので相続人等の負担は最小限で済みますし、公平公正な専門家が介入することで無用なトラブルが起きることを防止できます。
ページのトップへ
四 自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
遺言書にはいろいろな種類がありますが、一般的に作成されるのは「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」の二種類です。
自筆証書遺言は「自分で手書きする遺言書」です。対して公正証書遺言は「公証人という中立公正な立場の法律専門家が遺言書を作りたい人から聞き取りを行い、その内容に従って作成する遺言書」です。
01 比較表
| 自筆の遺言書を作成した場合 | 自筆の遺言を法務局で保管する制度を利用した場合 | 公正証書の遺言書を作成した場合 | |
|---|---|---|---|
| 費用 | かからない (専門家手数料は別) |
未定(数千円程度) | 数万円~ |
| 作成の手間 | 慣れたら手間はかからない | 保管申請の手間がかかる | 公証人との打ち合わせに手間がかかる |
| 作成時に証人二名が | いらない | いらない | いる |
| 紛失、変造の可能性 | ある | ない | ない |
| 保存の難しさ | 難しい | 易しい | 易しい |
| 死亡後に家庭裁判所での検認が | 必要 | 不要 | 不要 |
| 内容について争いに | なりやすい | なりやすい | なりにくい |
| 内容の変更・修正は | できる | できる | できる |
| 作成者への負担は | 軽い | やや重い | 重い |
| 相続人への負担は | 重い | やや重い | 軽い |
- 1. 費用に関する違い
- 自筆証書遺言は自身で作成しますので、専門家に依頼しない限りお金はかかりません。(ただし、自筆の遺言書を法務局で保管してもらう制度を利用した場合は、保管料(数千円程度?)の支払いが必要です。)対して公正証書遺言は公証人に作成手数料(数万円~)を支払う必要があります。
- 2. 作成にかかる手間
-
自筆証書遺言は慣れてしまえばすぐに作ることができます。書き方に決まりはありますが、それさえ守れば手間はかかりません。最も単純な内容であれば30分もかからずに出来てしまいます。
手書きの遺言書を法務局で保管してもらう制度を利用する場合は、必ず遺言者(遺言書を作成した本人)が遺言者の住所地、本籍地、所有する不動産の所在地のいずれかの法務局に行って、直接手続きしなければなりません。本人が出向くことができない場合は、保管制度を利用することはできません。
保管の申請は、ただ遺言書を持って行けば良いのではなく、遺言書の他に申請書、身分証明書等が必要なので、それらを用意する手間はかかります。
対して公正証書遺言は公証人との打ち合わせが必要なので早くても数日はかかりますし、少なくとも一度は公証人と面会しないといけないので手間はかかります。
- 3. 遺言書作成時に必要な「証人」
- 自筆証書遺言は基本的に「一人で」作成することができます。対して公正証書遺言は公証人との面会の際に「立会人」が二人必要です。この立会人を「証人」と言いますが、基本的には「遺言書の内容に利害関係がなく」、「遺言書の内容を口外しない信用できる人」に頼まないといけません。頼めそうな人がいない場合は法律専門家や公証役場の職員に依頼することもあります。
- 4. 紛失・変造の可能性・保存の難しさ
-
自筆証書遺言は自身で保管場所を決めないといけません。盗難や紛失のおそれのない場所に保管しなければなりませんが、相続人が見つけられない場所に隠してしまうわけにもいきません。銀行の貸金庫に入れておくこともできますが、管理料が発生します。
自筆遺言書の保管制度を利用した場合は、法務局で相当の長期間保管されますし、その遺言書の作成者以外が原本を手に入れることはできませんので、紛失や変造の恐れもありません。また、保管申請時に支払う手数料はかかりますが、以降の保管料などの費用は発生しません。
公正証書遺言は一度作成すると原本は相当の長期間公証役場で保管されます。毎月保管料を払う必要もありません。仮に手元にある公正証書遺言の正本や謄本をこっそり書き換えたとしても原本と一致しなくなるので簡単に偽造や変造を証明することができます。
- 5. 内容について争いになりやすいか、なりにくいか?
-
手書きの遺言書は内容の適否をめぐってしばしば争いになります。本人が書いたものではない、本人を騙して書かせたものだ、書いたときには認知症になってはず等々、様々な理由で裁判になります。
遺言書の保管制度を利用した場合については、本人確認や遺言書が法定の様式を満たしているかの確認だけはされますが、内容についての正確性、適法性、厳密な意思確認などは行われないため、争いになる可能性は十分にあります。
対して公正証書遺言は外部の中立公正な専門家である公証人が厳密に本人の意思を確認して作成しますので、内容について争いになるケースは少なく、仮に裁判になったとしても公正証書遺言は非常に強力な証拠力を持ちます。
- 6. 内容の変更の可否
-
遺言書は作成した後でも内容を変更することができます。これは自筆でも保管制度を利用した場合でも公正証書でも変わりません。ただし、後日の混乱を避けるため一般的には内容を変更するのではなく最初から作り直す方が無難です。
法務局に保管している遺言書を訂正する場合は、まずは遺言書の作成者が法務局に行き、遺言書の原本を返却してもらいます。返却された原本は破棄し、新たに作り直したものを再度、保管の申請を行います。
なお、返却された遺言書自体は有効なままですので、破棄せずに自宅等で保管していますと、その遺言書も有効な遺言書となりますので、十分に注意してください。
- 7. 作成者の負担、相続人の負担
-
通常、自筆証書遺言の方が作成者の負担は軽いです。しかし、法務局に保管されていない遺言書を使って遺産の名義変更手続等をする際は検認を受けなければなりませんし、内容の適否が問題になることもあり相続人に思わぬ負担をかけてしまうことがあります。
法務局での保管制度を利用した場合でも内容の適否が問題となることは十分に考えられますので、作成者の負担は少しで済みますが、相続人の負担も生じる危険性はあります。
対して、公正証書遺言は作成時には費用と手間がかかるので作成者の負担が重いですが、相続人の負担は非常に軽く済みます。
02 検認で起きる問題
法務局での保管制度を利用していない自筆証書遺言は当事者が勝手に開封することは出来ません。「家庭裁判所で検認を受けてから開封すること」と法律で決められています。検認とは遺言書の開封手続きです。司法書士に申立書の作成と戸籍謄本の収集を任せることはできますが、その場合は手数料がかかります。
- 1. 検認を受けるために必要な書類は?
- まず亡くなられた方の出生から死亡にいたるまでの全ての戸籍、相続人全員の戸籍が必要です。それに検認手続の申立書を添付して家庭裁判所に提出します。ここで必要な戸籍謄本の一式は遺言書が無い場合に必要になる戸籍謄本の一式と同じです。
- 2. 検認を行う旨の通知書が相続人全員に届く
- 家庭裁判所から相続人全員に検認手続の日を知らせる通知が届きます。期日に参加するかどうかは任意なので参加しないことも可能です。
- 3. 検認期日に遺言書を持参して、裁判所職員に開封してもらう。
- 検認後、検認済みの証明書を発行してもらいます。この検認済み証明書が無いと遺言書を財産名義の変更に使うことが出来ません。
03 自筆証書でも十分な場合、公正証書遺言が必要な場合
遺言書の効力自体は手書きの遺言書でも公正証書でも変わりませんので、絶対に公正証書でなければならないというわけではありません。
次のような事情がある場合は公正証書遺言をお勧めします。
- ■ 検認は面倒。遺産の名義変更が楽に早く済むなら遺言書の作成に多少の手間がかかっても良い
- ■ 出来るだけ家族の負担は軽くしたい
- ■ 利害関係人が多く、手書きの遺言書が問題になる可能性がある
ページのトップへ
五 自分で作る遺言書の書き方
自筆の遺言書を作成するときは、司法書士や行政書士の専門家に依頼しない限り内容は全て自分で考えて書くことになります。記載方法にはルールがあり、そのルール通りに記載しなければ遺産の名義変更手続きに使用できないどころか、遺言書自体が無効になってしまうこともあります。
01 自筆証書遺言の必須条件
自筆の遺言書の基本ルールは次の三つです。このルールを守っていない場合は遺言書そのものが無効となります。
- 1. 財産目録を除き、全て遺言書作成者の手書きであること
-
パソコンで作成された遺言書はもちろん、ビデオメッセージや代筆も認められません。よって、遺言書を手書きで作成する場合は少なくとも字が書ける状態でなければなりません。もし字が書けないが意思疎通に問題がないのであれば公正証書による遺言書を作成することになります。
ただし、2019年1月13日以降、遺言書の本文とは別に、財産目録(遺言書に記載する財産と現物が間違いなく照合できるように、財産の詳細を記載した書面)についてのみパソコンで作成したり、通帳の写しや登記事項証明書を添付したりすることが可能となりました。
もし、財産目録をパソコン等で作成する場合は、
①遺言書の本文と財産目録は必ず別の用紙に分けて記載しなければなりません。
②遺言書の本文には、例えば「財産目録1の不動産を〇〇に相続させる」等、財産目録との対応関係が分かるように作成すること(特に複数の財産目録が必要となる場合)
③財産目録には、1頁ごとに署名捺印をすること。通帳の写しや登記簿謄本を財産目録とする場合も同様に遺言書作成者の署名捺印をすること
④財産目録を二つ以上作成する場合は、「財産目録1」「財産目録2」のように、それぞれに番号を割り振り、遺言書本文の記載とズレがないように注意すること
が必要です。
簡単になったように感じますが、財産目録ごとに番号を書いていないケース、遺言書本文に「財産目録」としか書いておらず、どの財産目録なのか分からないケース、財産目録に署名捺印が足りていない等、遺言書として使用できなくなるトラブルに注意が必要です。
- 2. 作成した年月日が記載されていること
- 作成日は確実に特定できなければなりません。“吉日”等の特定できない記載は日付の記載として認められません。
- 3. 本人の署名、捺印がされていること
- 遺言者が署名、捺印します。使用する印鑑に規定はありませんが、出来るだけ実印を使用しましょう。
02 不動産の書き方
よくある間違いとして、不動産を「自宅」や「門司区の土地」と書いてしまう、あるいは「○○町一丁目×番△号の建物」といった住所で書いてしまう方がおられますが、これは遺産の名義変更手続きには使用できないおそれが非常に高いです。
不動産には「不動産専用の住所(土地なら地番、建物なら家屋番号)」があり、一般的な住所とは異なることが殆どです。遺言書を使って不動産の名義変更を行うためには遺言書に、土地については、「所在」「地番」「地目」「地積」、建物については「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を全て記載してある必要があります。それぞれの項目は最寄りの法務局で全部事項証明書(登記簿謄本)を取得して調べます。なお、法務局には記載する不動産に関する固定資産税の納税通知書を持参しておくと便利です。
このように不動産を遺言書に直接手書きで記載するのは負担が大きいですし、間違えやすいので、これから作成される方は、別途登記事項証明書(登記簿謄本)を法務局で取得し、それに署名捺印して財産目録とする方が良いでしょう。
- 土地の書き方(例)
-
遺言者は、○○に、下記の不動産を相続させる(遺贈する)。
所 在 福岡県北九州市門司区港町一丁目
地 番 ○番△
地 目 宅地
地 積 ~㎡
- 建物の書き方(例)
-
遺言者は、○○に、下記の不動産を相続させる(遺贈する)。
所 在 福岡県北九州市門司区港町一丁目○番地△
家屋番号 ○番△
種 類 ・・・
構 造 ~~
床 面 積 ~㎡
- マンションの書き方(例)
-
マンションの記載方法はかなり複雑です。間違いが非常に多い項目なので注意が必要です。
敷地権の記載がないマンションもありますが、その場合はマンションの敷地は「土地」として別に書きます。
一棟の建物の表示
所 在 福岡県北九州市門司区港町 ○番地△
建物の名称 ~~マンション(建物の名称がない場合もあります)
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根○階建
床 面 積 1階 ~㎡
2階 ~㎡
:
:
専有部分の建物の表示
家 屋 番 号 港町○番△の×××
建物の名称 ×××
種 類 □□
構 造 ~~~造1階建
床 面 積 □階部分
敷地権の表示
所在及び地番 福岡県北九州市門司区港町○番△
地 目 宅地
地 積 ~㎡
敷地権の種類 ○○権
敷地権の割合 ……分の~~~
- Q:遺言書が出てきましたが不動産の書き方が完全ではありませんでした。名義変更は無理ですか?
- A:正しい記載方法ではない遺言書だと原則として名義変更に使用することができません。但し、遺言書以外の資料から不動産が特定できる場合は認められることがあります。認められるかどうかは法務局の判断次第になりますので、諦めずに法務局に遺言書を持参して相談してみてください。
03 預貯金の書き方
預貯金は「金融機関名」「支店名」「預金の種別」「口座番号」が必要です。金額を記載する必要はありません。ネットバンキングを利用している場合も「金融機関名」「店番号(店名)」「口座番号」等、口座が間違いなく特定できる情報を記載します。
ゆうちょ銀行の場合は「ゆうちょ銀行」「店名(店番)」「記号」「番号」です。支店名や店番等は変更されている場合もありますので、最新の情報を確認して記載してください。
預貯金を直接遺言書本文に手書きすることに代えて、別紙の財産目録を作成する場合は、通帳の背表紙と裏表紙をコピーし、2枚ともに署名、捺印をし、「財産目録1」等の番号を振り、遺言書本文には「財産目録1の預貯金を○○に相続させる」等と記載するようにしましょう。
- 預貯金の書き方(例)
-
遺言者は、○○に、下記の預金の全額を相続させる(遺贈する)。
金融機関名 ○○銀行
支 店 名 ××支店
口座種別 普通預金(定期預金)
口座番号 ~~~~
- Q:「下記預金のうち、○万円を相続させる(遺贈する)」と書いてはダメですか?
- A:ダメではありませんが、お勧めはしません。口座の金額は変動するものなので、具体的な金額を書いてしまうと後で混乱の原因になります。
- Q:預金を二人以上に分けたいときはどう書けばいいですか?
- A:この場合も割合で分けるようにします。例えば、「下記預金は、2分の1を○○に相続させる(遺贈する)。残り2分の1は△△に相続させる(遺贈する)。」と書けば大丈夫です。
04 投資信託の書き方
投資信託は、定期的に送付される報告書などを参考に記載します。書き方は証券会社や投資商品の種類によって異なりますので一概には言えませんが、少なくとも具体的に特定させることは必要です。「証券会社名」「取扱店」「商品名」「口座番号」は書いておいた方が良いでしょう。
- Q:投資信託はそのまま引き継がせるのではなく、解約(売却)させたいのですが出来ますか?
- A:可能です。ただし、売却の時期によって譲渡所得税が生じる可能性がありますので注意が必要です。
05 株式の書き方
株式は、「会社名」「所有株数」「株券番号」等を記載します。株券番号等が無いことも多いと思いますが、その場合は「会社名」と「株式数」のみを記載します。
二人以上に分ける場合は「それぞれ○○に△株、××に□株を相続させる(遺贈する)」と記載します。
- 株式の書き方(例)
-
遺言者は、○○に下記遺産の全部(△株)を相続させる(遺贈する)
会 社 名:株式会社□□
所有株式数:・・・株
06 「相続させる」と「遺贈する」の使い分け
その遺産を継ぐ人が相続人である場合は「~を相続させる」と書きます。相続人以外であれば「~を遺贈する」と書きます。ここで言う相続人とは「遺言書の作成時点で死んだとしたら相続人になる人」のことを言います。
相続人の判断は細かい例外まで含めると大変なので、基本的な部分のみをまとめています。分かりにくい場合は法律専門家にお尋ねください。
- 1. 配偶者
- 戸籍上、婚姻関係にある夫(妻)です。離婚している場合は相続人ではありません。
- 2. 直系卑属(子供、孫、ひ孫等)
- 遺言者から見て、子供、孫、ひ孫等を「直系卑属」と呼びます。この直系卑属のうち、「遺言書の作成時点で存命の直系卑属のうち、遺言者にもっとも近い親等の者」が暫定的な相続人です。これらの者に遺産を渡す場合は「相続させる」を使います。そうではない場合は「遺贈する」となります。
- 3. 存命の直系卑属が一人もいない場合は直系尊属(父母、祖父母、曾祖父母等)
- 直系卑属が誰もいない場合は、遺言者から見て父母、祖父母、曾祖父母等を「直系尊属」と呼びます。この直系尊属のうち、「遺言書の作成時点で存命の直系尊属のうち、遺言者にもっとも近い親等の者」が暫定的な相続人です。
- 4. 存命の直系卑属、直系尊属が誰もいない場合は兄弟姉妹
- 存命の直系卑属・直系尊属が既に誰もいない場合は遺言者の存命している兄弟姉妹が相続人となります。ただし、既に死亡している兄弟姉妹に子供(遺言者から見て甥・姪)が存命している場合はその甥・姪が相続人となります。
07 遺言執行者の書き方
遺言執行者は未成年者及び破産者以外であれば制限はありませんので、その遺産を受け取る人自身が遺言執行者になることも可能です。但し、複数の遺産がある場合や第三者に寄付(遺贈)する場合、あるいは当事者間でトラブルになる可能性が少しでもある場合は利害関係のない法律専門家を遺言執行者にした方が安全です。
遺言執行者の権限に関する記載は無くても良いですが、委任する事項を明確にするため記載しておくことをお勧めします。
- 遺言執行者の書き方(例)
-
この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
福岡県北九州市門司区港町6番5号KAプラザ3F
司法書士 河喜多 洋(昭和53年7月31日生)
遺言者は、遺言執行者に対し、~~その他遺言の執行に必要な一切の行為に関する権限を与える。
- Q:遺言者が亡くなり、遺言執行者になりました。まず何から始めたら良いでしょうか?
- A:まず相続人全員及び遺贈を受ける人に対して自身が遺言執行者になったこと及び遺言書の内容を通知します。通知書は念のため配達記録郵便等で郵送しておいた方が良いでしょう。その後、遺産の目録を作成し、相続人等に交付します。金融機関には遺言者死亡の連絡と自身が遺言執行者になったことを連絡しておきます。
- Q:遺言執行者として遺言書通りの手続きをしようとしたのですが、相続人が協力してくれません。
- A:法律上、遺言執行者がいる場合、相続人は遺言の執行を妨害してはいけません。また遺言書の内容に反した手続をすることもできません。こうした行為が発覚した場合、遺言執行者はその相続人に対してその行為を止めさせたり、消費してしまった遺産を元に戻すよう請求することになります。
- Q:遺言執行者が遺言書通りに手続を進めてくれません。
- A:遺言執行者は、財産目録を作成し相続人に交付する義務とともに遺言書の内容通りに手続を進める義務があります。手続きを進めるために障害が発生している場合はその障害を排除しなければなりません。こうした義務に違反した場合、利害関係を有する人は家庭裁判所に対して遺言執行者の解任を申し立てることができます。
08 条件付き条項の書き方
遺言書には様々な条件や制約を付けることができます。ただし、付けた条件や制約が必ずしも効力を持つというわけではありません。
- 1. 遺産を受け取る予定の人が遺言者よりも先に死んでしまった場合の条項
-
遺産の譲渡を行う遺言書の条項は遺産の受取人が存命であることが条件です。もし存命でない場合はその遺産は引き継ぎ先が指定されていない遺産として遺産分割協議が必要になります。そこで、このような場合に備えて次順位でその遺産を受け取る権利を有する人を指定することができます。
例:「遺言者より前に又は遺言者と同時に○○が死亡した場合は、遺言者は、第×条に記載した遺産を△△に相続させる(遺贈する)」
- 2. 遺産を受け取ることが出来る条件として何らかの義務(負担)を負わせる条項
-
例えば、飼い犬の飼育費を遺す代わりに、その世話を任せたい場合等に条件を付けます。もし条件を守らずに遺産を受け取った場合、他の相続人や遺言執行者等が条件を守るよう請求することができます。ただし、どんな条件でも付けることができるわけではなく、公序良俗に反する条件や実現不能な条件、過剰な負担を強いる場合等は条件として認められない可能性があります。
例:「第○条記載の遺産は、○○が・・・することを条件として、相続させる(遺贈する)」
- 3. 遺産分割協議を禁止する条項
-
遺言書がある場合でも相続人全員が合意して遺産分割協議をすることは可能とされています。そこで、別途の遺産分割協議を禁止する旨の条項を入れておくことができます。対象は「遺産全部」でも「特定の遺産」でも大丈夫です。ただし、禁止期間には上限があり、最大5年間です。
例:遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割を相続開始のときから5年間禁止する。
09 配偶者居住権の書き方
遺言書によって被相続人(遺産を所有したまま亡くなった方)の自宅を、自身の配偶者(戸籍上の夫、妻)に対して残したい(名義を配偶者にしたい)場合は、自宅の所有権そのものを配偶者に相続させるよう記載する方法のほかに、「配偶者居住権を設定する旨の記載を遺言書に入れておく」方法ができるようになりました。配偶者居住権を設定する場合は、所有者(登記簿上の名義人)を配偶者以外にすることになります。「配偶者に住み続けて欲しいが、名義人は別が良い」という場合に有効な方法です。配偶者居住権を設定することで、配偶者は無償で終生、被相続人の死亡後も自宅に住み続けることができます。
配偶者居住権を遺言書に記載できる条件は以下のとおりです。
①現在の建物の名義が「遺言者(遺言書を作成する者)が単独で所有していること」又は「遺言者の配偶者と共有名義であること」
②遺言者と配偶者の自宅であり、被相続人の死亡時点でお互いその建物に居住していること
③遺言書の作成日付は2020年4月1日以降であること
- 配偶者居住権の書き方(例)
-
遺言者は、私の配偶者である○○のために、下記の自宅不動産に配偶者居住権を設定する。存続期間は、配偶者が死亡するまでとする。
所 在 福岡県北九州市門司区港町一丁目○番地△
家屋番号 ○番△
種 類 ・・・
構 造 ~~
床 面 積 ~㎡※配偶者居住権を遺言書に記載していたとしても、被相続人の死亡後に配偶者居住権の登記をしなければ、他者に「この建物に住み続ける権利がある」と主張することはできません。できれば、相続による名義変更の手続きと同時に配偶者居住権の登記を申請する方が望ましいです。
また、配偶者居住権は他人に売却、譲渡することはできませんし、所有者(所有者として登記されている者)の承諾がない限り大幅なリフォームや賃貸はできません。
ページのトップへ
六 ご契約と手続きの流れ(自筆証書遺言の場合)
当方にご依頼いただいた場合のお手続の流れです。内容が単純な遺言書であれば2日程度で完成します。
01 ご相談、お見積りと契約
お客様の遺産を整理した後、希望する遺言の内容をお聞きしたうえで、費用のお見積りを致します。
費用にご承諾いただけましたら正式契約となります。
02 原案の作成
税金の調査、リスク調査などを行いながら、お聞きした内容に従って当方が遺言書の原案をお作り致します。同時に生前贈与等、他の方法がありましたら併せてご提案致します。
03 費用の御支払い、原案のお渡し
原案の調整等が終了致しましたら、最終原案をお渡しいたします。
費用の御支払いは最終原案のお渡し時になります。
04 用紙への記入・立会人の署名捺印
最終原案通りに手書きをしていただきます。使用する用紙はお客様自身でご準備いただいても結構ですが、こちらでご用意させていただくこともできます。当方が記入に立ち会う場合は立会人として署名捺印を致します。
05 確認、封印
内容に間違いがないことを確認した後、封筒に入れて密封して完了です。
ただし、自筆の遺言書を法務局で保管してもらう制度を利用する場合は、中身を法務局で確認してもらい、預ける作業があるため封筒に入れても密封はしません。
ページのトップへ
七 ご契約と手続きの流れ(公正証書遺言の場合)
当方にご依頼いただいた場合の手続の流れです。内容が単純でも完成まで1~2週間程度はかかります。
01 ご相談、仮契約
お客様の遺産を整理した後、希望する遺言の内容をお聞きしたうえで、費用のお見積りを致します。ただし、この段階では正確な金額をお出しすることが出来ませんので仮契約となります。
02 原案の決定
税金の調査、リスク調査などを行いながら、お聞きした内容に従って当方が遺言書の原案をお作り致します。同時に生前贈与等、他の方法がありましたら併せてご提案致します。
03 公証役場の費用見積を依頼、正式契約
原案の調整等が終了致しましたら、遺産の資料(全部事項証明書(登記簿謄本)、通帳の写し、保険証券等)、遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本と遺産をもらう人の住民票、戸籍謄本等を最終原案と一緒に公証役場に送り、費用の見積もりをもらいます。
公証役場の費用に当方の費用を加算して再度正式なお見積りをご提示致します。お見積りの額でご承諾いただければ正式契約となります。
04 公証役場での面会若しくは出張による面会+証人2名の立会い
公証役場で、公証人から遺言書の内容について口頭で確認を受けます。単純に「遺言書の内容に間違いないか?」ではなく、「○○の財産をどうしたいか?」ということを尋ねられます。その回答が遺言書の原案通りならば大丈夫です。よって、遺言者は遺言書の内容をしっかり把握していないと正確に回答できないことがあります。
この際、遺言者の証人として2名が立ち会います。遺言書の内容に利害関係が無く遺言書の内容を聞かれても問題ない人を連れてくる必要があります。もし手配が難しい場合はご相談ください。
もし入院・入所等で公証役場での面会ができない場合は、公証人に出張を依頼することができます。ただし、その場合は本来の費用よりも高くなります。
05 費用の支払い、遺言書正本の受領
確認完了後、遺言書の原本に遺言者、公証人、証人それぞれが署名・捺印します。原本は公証役場にて保管され、遺言書は正本を受領します。正本に署名・捺印はしませんが、問題なく遺産相続手続に使用することができます。また、別途謄本手数料がかかりますが、希望すれば「公正証書遺言の謄本」も交付されます。謄本は「正本のコピー」という扱いです。謄本をもらうかどうかは任意ですが、遺言者以外で遺言の存在を把握しておいてほしい人がいれば、謄本を交付してもらって渡すようにすると良いでしょう。
なお、謄本で手続きできるかどうかはその申請先によって異なります。
ページのトップへ
八 主な費用
自筆証書遺言の場合は原案作成の手数料のみですが、公正証書遺言の場合は専門家の手数料に併せて公証役場に支払う手数料が加算されます。
01 自筆証書遺言の場合
| 原案作成料 | 30,000円(税別) ※遺言書のページ数が4ページ以上になるときは、1ページにつき10,000円(税別)を加算 |
|---|---|
| 作成立会日当 | 10,000円(半日)~20,000円(全日)(税別) |
02 公正証書遺言の場合
| 原案作成料 | 30,000円(税別) |
|---|---|
| 遺言書作成立会い | 20,000円(税別)+公証役場の手数料 |
03 公証役場に支払う手数料の計算方法(概算)
公証役場に支払う手数料は「記載する遺産の総額」ではなく「遺産を受け取る人ごとに」別々に計算して合計した金額が手数料となります。例えば、Aさんに100万円の遺産、Bさんに300万円の遺産を相続させる遺言書の場合は、「遺産額が400万円なので11,000円」ではなく、「Aさん分が100万円なので5000円、Bさん分が11,000円なので、手数料は17,000円」となります。
謄本の有無や証書のページ数によって多少変わりますが、概ねこの程度の金額がかかります。
なお、公証役場に支払う手数料に消費税はかかりません。
- 1. 基本となる手数料
-
受け取る遺産の額 手数料額 ~ 100万円迄 5000円 100万円超~ 200万円迄 7000円 200万円超~ 500万円迄 11000円 500万円超~1000万円迄 17000円 100万円超~3000万円迄 23000円 3000万円超~5000万円迄 29000円 5000万円超~1億円迄 43000円 1億円超~3億円迄 43000円
+超過額5000万円迄ごとに13000円を加算3億円超~10億円迄 95000円
+超過額5000万円迄ごとに11000円を加算10億円超~ 249000円
+超過額5000万円迄ごとに8000円を加算
- 2. 遺言加算
- 公正証書遺言を作成する場合は別途の加算費用として更に11000円が加算されます。ただし、遺産の額が1億円を超える場合は別途公証役場に問い合わせが必要です。
- 3. 出張日当
- 公証人に出張を依頼する場合は1日あたり2万円(4時間までの出張であれば1万円)が別途加算されます。
- 4. 病床執務加算
- 公証役場に出張してもらう場合、基本手数料が1.5倍になります。
- 5. 財産の算定
- 不動産は固定資産税評価額(通称、「評価額」)を価格とします。預貯金はその時点での残額を財産額とします。
- 6. 算定不能の条項
- お金に換算できない事項(祭祀主催者の指定等)を記載する場合は原則として1事項につき11000円が加算されます。
04 遺言信託(遺産承継業務)も依頼する場合
(但し、この金額が30万円を下回る場合は30万円+消費税)
遺言信託の費用は、遺言者の死亡後のお手続時にお支払いいただきます。
※戸籍謄本等の取得に必要な発行手数料、郵送料等の実費は別途頂戴いたします。
※税理士又は社会保険労務士にご依頼いただく場合は別途報酬等の諸費用が発生します。
※不動産は「相続発生時の年度における固定資産税評価額」を遺産額とします。
※投資信託は「相続発生時から最も近い時点での評価額」を遺産額とします。
ページのトップへ
九 当事務所にご依頼いただくメリット
01 法律に適合する間違いのない遺言書を短期間で作成することができます!
専門家の手を借りずに作成された自筆証書遺言は不備が多くあります。そもそも遺言書として認められないものや、名義変更には使用できないものが本当に多く見受けられます。
専門家に頼ることなく作成された完璧な自筆証書遺言を見たこともありますが、関連書籍を何冊も熟読して勉強し、何日もかけて作成されたそうです。それが苦ではないのであれば良いのですが、専門家であれば安全で確実な遺言書が短期間(最短で即日)で作成できます。
02 書籍やインターネットには無い独自のノウハウで更に便利な遺言書をご提案します!
遺言書を書いてまで遺したいと思った大切な財産を亡くなるその日まで守るためには?
税金や遺留分のことまで考えて作成されましたか?
お客様ご自身でも「とりあえずの遺言書」は作成できます。しかし、プロならではの視点やノウハウを取り入れて「もっと安心・安全で、便利な遺言書」にすると、ご家族はもっと楽が出来るようになります。
03 公正証書遺言でも面倒な手続きは全てお任せ!公証役場への送迎も承ります!
安全で確実、作成から保管まで全部お任せの公正証書遺言ですが、見積もりに必要な書類の準備や公証人との打ち合わせ、証人の手配など、面倒なことが難点です。
お任せいただければ、これらの準備は全て当方で行います。お客様は当方との打ち合わせと公証人との面会だけで大丈夫です。公証役場への送迎も無料で承ります。お気軽にお申し付けください。
04 遺言信託も一緒にご依頼いただけます!
遺言書を作ってもその内容の通りに遺産を分けることが出来なければ意味がありません。例えば、遺産の一部を寄付したいときや親族以外に遺したい場合、あるいは相続人が遺言書の通りに分けてくれるか不安な場合は遺言信託の利用をお勧めします。当方では、遺言信託(遺産承継)の業務にも対応しております。
なお、一部の金融機関でも遺言信託の業務を行っておりますが、一般的に手数料が100万円程かかってしまいます。また、司法書士や弁護士の費用は別途支払う必要がありますので割高です。
遺言信託の費用を抑えたい場合は法律専門家にご依頼ください。
05 遺言書の作成だけでなく、幅広く相続対策をご案内致します!
当事務所には遺されるご家族に負担をかけたくないから遺言書を作りたいとお考えの方が殆どです。それは決して間違いではないのですが、相続の対策はただ遺言書を作ればいいというものではありません。例えば、葬儀の内容や友人・知人関係の連絡先、かかりつけの病院等々、遺言書に書くほどでなくとも親族に知らせておいた方が良い情報はたくさんあります。
当事務所では、遺言書の内容だけではなく、その動機や様々なご事情もお聞きしながら、お客様のご事情に合わせてエンディングノート、リビング・ウィル(尊厳死宣言証書)の作成などもご提案をしております。
ページのトップへ

-
〒801-0852
福岡県北九州市門司区港町6番5号KAプラザ1F
営業時間:平日(月~金曜日)9時30分~17時30分まで
※営業時間外・定休日でも前日までにご予約いただければ
対応させて頂きます